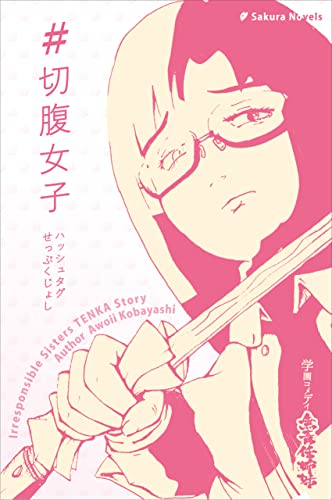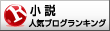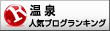この記事は以下の過去記事に関する記述です。
小説に掲げた難病について、詳細な説明をせぬまま展開したところ、審査員が「病名が分からないからリアリティが無くて安っぽい」といい、それに対して別の審査員が「分からなくて救われた」と言った、ということを聞いた。
作中の難病の未設定について、ぼくも全く意識しなかったわけではない。「物語の風合いを考えて、そこは敢えて触れない方が重たくならないし、むしろこの物語でそれは些末事である」と思っていた。
その一方で、物語のわりに、難病とその背後に暗示される「死」の比重が大きすぎ、どこかアンバランスな感じがしていて、「はてどうしたものか」と懸念していたのも、事実である。
評をふまえて友人らに意見を求めると、「これは現況のままに据え置くが得策で、審査員の言うようにこまごま設定するのは無駄で野暮」という声が多かった。ぼくも同感で、くだんの審査員のことを「三代目金馬を解せない久保田万太郎」のごとく思ったものだ。
ところがだ。
審査会を終えてブログにし、知り合いにそれを触れ回っていた際、自ブログの過去記事で落語論評をしたものがあって、何気なく読み返して「あッ」と思った。
それは桃月庵白酒師匠の「代書」を評した記事で、自分で次のようなことを書いている。
「くすぐりだくさんでよく笑わせてもらったが、ぼくとしてはかなり異色な感じがした。というのは、この代書は時代性が消去されていた 「文盲と代書屋が存在する時点で察せよ」というのはおいといて。
(中略)
「時代性が曖昧だと、聞き手は噺に入り込もうとしても見えない力で拒まれる。逐一笑えるんだけど、個々のくすぐりで笑っているのであり、ストーリーとして笑っている感じではなかった。
この落語は実際に会場で聴いていて、満点のウケだった。聴衆はゲラゲラ笑っている。ぼくも楽しんでいたが、内心この「時代性」の欠如が引っ掛かって、ゲラゲラとまではいかなかった。あとでその話を誰かにしても共感をえられなかった。「あの噺にそこまで時代は関係なかったよ」「むしろ普遍的な噺ってことじゃないかね」。しかたなくブログに書いて留飲を下げるしかなかったことを覚えている。
たぶん、ぼくは普段から落語の音源をききあさっているので、多少なり耳が肥えていて、多くの聴衆が気にならなかった「時代性」のアラに、気付いてしまったのだろう。そのちいちゃな気付きは、決して全体を損なうほどの瑕疵ではないのだが、ちょっとでも気づいたばっかりに、ぼくの目から噺の明度を下げてしまった。
ぼくが「あッ」と思ったのは、まさにここだ。
おそらく、これと同様の違和感が、拙作を読んだ審査員の感覚に生じたのではないか。それが難病のディテール不足への責めにつながったのではないか。
きっと審査員氏は、おびただしい読書と執筆を通し、難病にせよ事故にせよ、死を物語で扱う際のありうべき位相に精通し、鋭敏な感覚を会得しているのだ。ゆえに安直に死を持ち出したぼくの作品について、他の誰も気付かないことを独自の鋭敏さで察知し、違和感を抱き、いくら軽い風合いの作品だからといって看過できなかったのではないか。
そう気づいた瞬間、審査員の批判に抱いたおのれの反感が、まるっきり自己矛盾の代物だと気付いて、おそろしく恥じ入った。
氏に反論した別の審査員の「病名が分からなくて救われた」だが、これは氏なりの別途の研磨の結果か、それとも鋭敏審査員へのたんなる切り返しなのか、それはわからないけれども、なんにせよ多少目はつむれるということだから、いささか我々に近い感覚なのかもしれぬ。
では当該の作品において、標榜する風合いは保持するものとし、難病と死はいかに語られるべきだったのだろうか。死の様相に鋭敏な審査員先生が読む前提で表現するとなると、難病の仔細をしっかり書かねばならないが、さあ、どんなふうに? いかに?
おそらく上手の筆は、うまく書きおおせるのだろう。難病と死を小さな襞の影まで描きつつ、ナンセンスな笑いを保証するのだろう。
嗚呼、正直ぼくにはできない。
方策が丸きり思いつかない。
また、たとえ難病や死に、思い入れとこだわりを持つことができたとしても、それを文にするだけの言葉の力を持っていない。つまり、ぼくには現状、死について書く力量がない。ということは、結論として、そもそもこの物語を書くべきではなく・書く資格もなかったのである。
よくよく思い返せば、ぼくも「作品における死」に違和感を抱いた経験があった。
その昔、アルフというアメリカンコメディがあった。子供向けのホームドラマである。ある回で、アルフなる毛むくじゃらが、いたずらで庭に落とし穴を掘ったところ、その家の叔父がはまって死亡する、という話があった。叔父は画面に登場することなく、視聴者にはながれで死が伝えられ、登場人物はあたふたする。ぼくは子供時分これを見て、死が極めて浮薄に扱われ、しかもその後、大した物語的位置を占めることなく番組が終わったことに、なんとも言えないしっくりこなさを感じたものだ。翌日学校でこの話を友人にしたら、見ていた者は同じことを感じていた。これは日本人なら子供でも持っている死生観と、アメリカ的な死の間に、乖離があるのだと思う。
さてぼくは、2つ上の段落の末尾で、「そもそもこの物語を書くべきではなく・資格もなかった」と言った。言っておきながら内心じつは承服できない、否、するわけにいかない思いに駆られている。
なぜならその発想は、人が表現しようとする根源的欲求から、苦手部分をこさぎとり、誤魔化すことに過ぎないからだ。
表現したいことがあっても、「これはぼくにはむりだから」「これは厄介なテーマだから」と言って迂回していたら、表現のさらに上層に占める「創造」という究極目標を放棄することになる。それを放棄してできる作品は、いったいなんだろうか? 本末転倒ではないか?
結局、表現する者は、分からないなりに、未熟ななりに、前に進み続けることしかできない。そして、指摘され、転倒して、過ちを認めて、学びを深め、それを正して、と繰り返しながら、やっていくしかない。それは時間のかかることであると思う。だがその登攀こそが、万象を理解する契機となり、喜びとなり、面白みとなるのだ、 と、信じている。