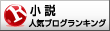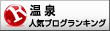表題の興行が2023年5月21日(日)に鹿児島市の黎明館で催された。主催は落語を愉しむ会。『ゆるいと亭』様のお席である。良い席をリーズナブルに展開されるお席亭にはいつも感謝している。
正直いうと、柳家三三(やなぎや・さんざ)師匠について、名前は知っていたが、詳しい知識はなかった。小三治一門で、落語の賞を総なめにしているのは知っていた。あと、お弟子さんが芸術協会に移籍した顛末の云々を動画共有サイトで視た記憶がある。実際の噺となると、ライブは初めて。動画では何個か視たような気がする。そういうわけで、事前の期待値が高かったかというと、ぶっちゃけそれほどではなかった。
三三師の大師匠・五代目柳家小さんは「おかしみ」の芸だったと思う。にじみ出る人柄の芸。当然他人は真似できない。直弟子たちは天衣無縫のその「おかしみ」を「おかしさ」として写すのが限界だったように思う。それはあたかも塑像を写真に撮るようなもの、立体を平面に焼き付けるに等しい。だが直弟子たちは師匠の「おかしみ」を生で知っているから、みずから映し出す「おかしさ」のエッジに自分なりのベベルを掛けることはできた。実際、直弟子には名人上手が多い。談志、馬風、小三治等々……。
しかしその孫弟子の代となると、果たしてどうだろう? 落語の芸は必ずしも師匠の芸風を受け継ぐものではないが、少なくとも対比の中で芸脈は紡がれていく。写真をまた写真に撮るか。それとも3Dプリンタで奥行きまで製造するか。あるいはそれらとは全く無関係な筆法を編み出すか。
事前に三三師匠のインタビュー記事を読んだところ、なんと、師匠小三治から噺を教わったことはないとのこと。
なるほど……。
実はぼくにとってこれは好印象である。
そこは期待が持てた。
さて、高座を振り返ろう。
お席亭の開会の挨拶によると完売・満員御礼とのこと。見渡す限り全ての席が埋まっていた。大入叶。新型コロナが5類になったことの影響は大きい。旧に復し活気が戻っていることを、お席亭が心から喜んでおられることが分かった。
出囃子に乗り、舞台上手から三三師匠があらわれた。痩躯に小さな頭、髪は短く刈り込まれている。緑色の羽織が舞台奥のワインレッドの幕に映え、クリスマスか公〇党の選挙ポスターのようにコントラストが鮮やかだ。座布団に膝を折り深々とお辞儀。前座無しの完全独演である。
滑らかな「まくら」がはじまる。なんと口跡のよいことか。美声というのではないが、耳に心地よく、延々と聞いていられる。歯切れと間合いから器用な方だと察する。軽い笑いを存分に散りばめて客席が温まったところで噺に入った。
1席目『天災』
ガラッ八の親不孝な言動に耐えかねたご隠居が、八を心学者のもとへ送って性根を入れ替えさせようとする。八は諭されて考えを改めるが、その後は『子ほめ』『くやみ』のような落語世界お馴染み「勘違い模写」展開でオチとなる。
お馴染みといってもこの噺はいささか異質である。心学の説教臭さ。「クマ・ハチ・ご隠居」のような匿名性の世界に紅羅坊名丸などというゴテゴテした名の登場人物の存在。そしてなにより、主人公・八が多少なりとも心を入れ替えるという、落語世界の禁忌を犯すところに違和感がある。誰が言ったが「落語は人間の業の肯定」という解釈を、一瞬だが覆しかけるのである。そこにどうしても嘘臭さがでてしまうのだ。もとは説話なのだろうな。個人的にはあまり好きな噺ではない。
高座において、八が心を入れ替えるくだりでは、名丸の問いに説得力を持たせるためか、フレーズのリフレインが多用されていた。低めの学究調で『いかがかな?』『どうかな?』という具合である。独演会は開場13時半・開演14時。観客のほとんどは昼食を済ませてきただろう。ぼくもそうだ。舟を漕ぎそうになる中、実際いくつかの頭はこっくりこっくりやっていた。無理もないよなと思っていたら、なんと、高座から三三師匠が噺に織り交ぜて起こしにかかる事態に。随所に笑いは散りばめられていたが、さざなみのようだった。
2席目『お血脈』
続けて二席目。やはりまくらがたのしい。話がおもしろい。この師匠のおしゃべりは粒だっている。漫談が続く中、師匠が「噺はもうはじまってますから。2席目はもう自由時間。こんな感じですからね」と念を押すところがまた愉快である。もっとも、後から思うとこれは意外に重要な線引きだったかもしれない。『お血脈』は地噺で、ナレーション的に噺が進む。漫談は極めて自然にお血脈へと流れ込んだが、聴衆の中でこの噺を聞いたことの無い人は、「いつはじまるのかな?」とずっとじりじりしていたかもしれない。そういう人に対して念を押しておくのは意味があるだろう。
この日三席の中でもっとも楽しめた。公演後SNS上でもそういう書き込みが見受けられた。まくらのうまい師匠だから、地噺は相性がいいだろう。いかにも自然に噺に入り、入り込んだかと思ったらまた引きずり出す。いくら地噺といっても本来噺世界の外枠からはさほど逸脱しないものだが、師匠はぐーんと飛び出して、また正しく戻ってくる。噺の芯がしっかりしているので、脱線しっぱなしや聴衆を遠心力で軌道外に放り出すことはない。ここまで雑談調のまま先に進むお血脈はなかなかないだろう。
また、これほどライブに合う噺もないと思った。その時その場の話を盛り込めるので、唯一無二の時間を過ごしている感動がある。
<仲入り>
3席目『橋場の雪』
珍しい噺である。最初は思い出せず『夢の酒』かなと思った。後で調べたら、橋場の雪がまずあって、のちに夢の酒ができたのだそうだ。八代目文楽も最初は橋場の雪を演っていたとか。
雪の夜に浮き上がるご新造の白い顔、向島料亭の灯。静と動、しじまとにぎわい。江戸の夜を川と雪という自然の舞台装置を用いて俯瞰する視点は、いかにも文学的で、独特の情緒を醸し出している。
しかしねえ。これは全編夢だし、夢とはいえ定吉が舟を廻せるというのは、どうも強引だ。川を行ったり来たりするのもストーリーとしてくどい。『夢の酒』を知らなければ何とも思わなかったかもしれないが、知っているばかりに、噺の非合理性や悪循環が鼻につき、筋立てを不格好に感じてしまう。のちに改変されたのは当然かもしれない。創作話というものは、とりあえず手を尽くしきった状態において、最適化されていてしかるべきだと思う。「それを落語の噺に求めるのは野暮だよ」と言うかもしれないが、実際いい噺はとことん合理的で無駄がないものだ。『頭山』や『粗忽長屋』には一句も引けない完成度がある。
こうなると噺は演者の仕型にかかってくるわけだが、三三師匠の『橋場の雪』、さすが見事な一席だった。若旦那の夢見を聞いて泣く女房のいじらしさ、かいがいしい様子の大旦那、もちろん主役の若旦那、みなしっかりと目に浮かぶ。先述の江戸情緒も絵巻を見るようで美しい。
ただ、「初夏の昼間に雪の夜の噺?」と思ったことを告白しておこう。涼しくなればってこと?
総括
はじめて拝見する柳家三三師匠の高座、印象に残ったのは「まくらの楽しさ」である。ちょっとしたジョークが自然に振り出され、きれいにガスが抜ける風船のようにぷーッと笑いになって後に引かない。
師匠小三治に噺を習ったことは無いとのことだが、かの師匠もまくらの名人の聞こえが高かった。今に思うと、小三治師匠のまくらはストーリーラインが二本くらいあってそれが二重らせんのように絡み合いながら先へ進んでいくところから、一定程度ネタ化している趣があった。だからこそドリアンやらバイクやらはちみつやら、いまだに人口に膾炙している。
三三師匠の話がそうかといえば、そうではない。が、そうである必要はないし、そんなことはどうでもいい。
でも……ちょっとしたジョークが続くくらいでは、どうしても笑いが浅くなる。ジョークは「おかしさ」の笑いであり、皮相である。やはり客としては話から醸し出されるエッセンス、すなわち「おかしみ」で笑わせてもらいたいものだ。思い出し笑いが後を引くような。
そういえば、ひとつ謎が残った。
『お血脈』のまくらで師匠は「私たち噺家は何の演目を出すかを高座に上がってお客様の様子を見て決める」とおっしゃった。
とすると、一席目が『天災』になったのも、やはりそうなのだろうか? しかしなぜ?
*
さいごに自分自身について思ったことを言います。それは「ああぼくってやっぱり田舎者だな」ということです。クサくないと感情移入できないところがあるようです。本寸法、江戸前の芸というのがどういうものなのか分からない……もしかしたら、目撃しても分からないかもしれない。一生分からないかもしれない。
近々、別名義で出してる落語評論を読んでくださった方に会うので、ちょっとそのへんのことを聞いてみたいと思います。江戸っ子で卒寿を過ぎても寄席通い。戦後に人形町末広で文楽・志ん生・可楽・三亀松らの芸を観てきたという生き字引です。
*
告知です。現在銭湯戯画イラスト展を開催中です。
足を運びなさい。きみ。