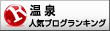表題の興行が2022年11月13日(日)に鹿児島市の黎明館で催された。主催は落語を愉しむ会。『ゆるいと亭』様のお席である。
演者の三代目桃月庵白酒師匠は芸歴三〇年。当地鹿児島のご出身。里帰り興行である。同日、同市の別の箱でこのたび真打昇進した春風亭柳雀師匠も里帰り興行を行っている。こちらは郷土で初独演会とのこと。
白酒師匠は冒頭「芸歴30年なんてね」「この世界50は若手」「金翁師匠なんか80年もされて」と、特に節目を意識されていないようだったが、演目を振り返ってみると、何か期するものがあったのではないか。ネタは「代書」「甲府い」「宿屋の富」だった。
「代書」はこれから就職しようとする主人公の前向きな噺。「甲府い」は苦労人の出世譚。「宿屋の富」は宝くじが当たっておめでたい噺。
出世&めでたい尽くしである。
ちなみに柳雀師匠は「皿屋敷」「転宅」「御神酒徳利」をかけたらしい。前二つはともかく、最後の一席は出世成功譚だ。
なんとなく、ご両名とも郷土に錦を飾るにふさわしい演目をあげているような気がする(リクエストがあったのかもしれないけど)。
白酒師匠、初見であった。ネットでも視たことが無かった。風貌と「人気がある」という噂を知っていただけである。
風貌はどっしりとして、お顔は愛嬌があり、五分刈りのためか腕白少年みたいな感じがする。
五街道雲助師匠のご一門だ。この師匠は何度か観覧し、ネットでも視たことがあったが、変幻自在に噺を操り、きめこまかなわりに意外に大胆。それでいて陽に振り切らず、なにかこうひたひたとしたおかしみを感じた記憶がある(ぼくの中でなぜか春風亭一朝師匠と陰陽の関係にある)。
そういう師匠のお弟子さんで、あの風貌だから、てっきり強打者系の爆笑王かと思ったところ……全然違った!
端正も端正。声が通り、仕草がきれい。
今は宗家ごとの芸風というのはあまり語られないが、三遊のように大きなコントラストを付けるでもなく、柳のように淡々としているのでもなく……ふと「そうか、ルーツは古今亭か」と思ってみたりした。
ひょうひょうとして伸びのある高座。くさいところがそれほどないのに、ずっと惹きつけ続ける。ぼくなぞはわがままな性格で、長時間じっとしていられないから、好きな落語でもちょいちょいくさいところがないと持ちこたえられないのだが、今回はそんなことを何も考えなくても聴き続けることができ、楽しい時間はあっという間に過ぎ去った。聴衆として完全にコントロールされた。これはいい。こうでなくちゃならない。
では三席を振り返ってみよう。
一席目「代書屋」
まくらは識字率の話を振られたと思う。くすぐりだくさんでよく笑わせてもらったが、ぼくとしてはかなり異色な感じがした。というのは、この代書は時代性が消去されていた 「文盲と代書屋が存在する時点で察せよ」というのはおいといて。
この噺は先代米團治が実際に代書業を営んだ経験をネタにした上方噺で、圓朝を区切りとする古典/新作の別で分けると新作に入る。しかし原文はそこそこ時代がかっており、折々あらわれるフレーズはもはや「近代」である。「尋常小学校」「朝鮮人」、枝雀の「ポン菓子」なんかがそれで、いつとは言わなくともある種の時代を感じさせる。そしてそれは些細なようでいて実に大きな効果を与えている。物語世界の表現における時代や季節の表明は、見聞きする者に一つの印象の共有を要請する。それにより感情移入を促進するのである。
白酒師匠の代書は、現代といえば現代だし、かといって近代といっても通じる世界だったと思う。むろん、文盲と代書屋がいるから現代ではない。だが、登場人物の交わす言葉は現代のそれだった。このように時代性が曖昧だと、聞き手は噺に入り込もうとしても見えない力で拒まれる。逐一笑えるんだけど、個々のくすぐりで笑っているのであり、ストーリーとして笑っている感じではなかった。
もっとも、変に時代性がないことで噺から妙な重みがなくなり、一席目としてふさわしい程度に軽く聞けたかもしれない。そこはよかった。
二席目「甲府い」
確か「空腹だと人間いらいらしたりする」というまくらが振られたと思う。すばらしい一席で聞き入った。今日一の名演。
それにしても「甲府い」は落語オブ落語というべき噺である。これを文章に起こして読み直しても、一体何がおかしいのか分からない。下げにいたっては売り声のダジャレでくだらなさすら感じる。
しかしひとたび高座の名人にかかれば、これほどほっこりして、あたたかみのある、幸せな気分になれる噺はなだろう。下げのダジャレの売り声を、徐々に声を遠めにすれば、甲府に向かう若夫婦の背中が見えるようである。これは文章では再現できない。
それゆえに、この噺は、客がある程度落語耳を持っていることが前提のように思う。演る方は聞き手の耳を信じ、さらにいえば聞かせる自信がないとできないのではないか。
三席目「宿屋の富」
中入りをはさんで最後の噺。実は中入り中、「このあとどうなるのかな」と少々不安を覚えていた。というのは 中入り前の2席は端正ですばらしかった。だが、あまりにあくがなく、満足だけど満腹にならない感じがしていた。
「このまま最後の一席もそうだったら、なにかこう、非常に惜しい気分になるだろう」
少しぐらい乱暴で、クサいところがあってもいいのだが……と贅沢なことを願いつつ、三席目に臨んだ。
結果的に心配は杞憂であった。
噺は立ち上がりから翌日の湯島天神のシーンまでするするっと進んだ。大きく動いたのは、富突き前の人々の言い交し。そこで行われた「劇中劇」ならぬ登場人物の仕方噺のくだりから落語が弾けた。
それまで朝霞のように清らにうっすらと広がっていた噺全体の印象が、ここでぎゅっと凝集された。繰り返しのくだりがうまく作用し、聴衆にこれでもか、これでもかと笑いの契機をぶつけてくる。爆笑。客席の温度があがる。といって、別にそこで白酒師匠がこってりねっとり演りかたを変えたわけではない。筋に沿ってテンポを自在に操ってその高揚感を発現しているだけでである(「だけ」といっても名人芸だ)。結果クサくならずに爆笑のまま下げまで完走した。
ぼくは唖然とした。名人芸を見た気がした。三席を振り返ってみれば、仲入り前は適度に軽く、最後はずしっと。前菜と肉料理がちゃんとコースになっていた。
*
昨今人気の真打さんたちに対し、ぼくはちょっと否定的なところがある。「登場人物を聴衆に合わせようとしてデフォルメしすぎる」ところである。噺の人物がときおりこちらに目線を向け、語り掛ける。「おれって不幸だろう?」「この気苦労は滑稽だろう?」 ああ、このメタの違和感。気持ち悪さ。
これはおそらくテレビの弊害だろう。テレビの芸人は、お茶の間にも分かるようにキャラ造形を説明的にする。彼らにしてみれば、目の前に客がいないので受けてるかどうか分からず、保険をかける行為が説明ということになるのだろう。
だが落語でそれをやるのはナンセンスだ。芸人さんにはむしろ「分からん奴はついてこんでいい」くらいの気概でいてほしい。
と、こう思っていたことが、ぼくの中にいつのまにか、今の芸人さんへの偏見・先入観を産んでいたかもしれない。ぼくは白酒師匠を視たことがなかった。でも視たら……素晴らしかった! ほかにも視たことのない方が大勢いる。先日うかがった落語会では、新人さんの芸をみることがこちらの眼も肥やすとつくづく思った。
先入観は人生を損させる。
幸せになるために落語を聴こう。
そのために、広くおおらかに、くわずぎらいは止していこう。
おしまい