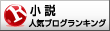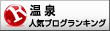驚いた。この「無責任落語録」シリーズ、1年9か月ぶりとは。サボり過ぎだろ。
別に反響がないからやんなかったとかではない。単に自分のうんちくがついえていた。情熱が下火になっていた。
談志が死に、円蔵が死に、歌丸さんが死んじゃって、ぼくの中でスーパーヒーローはみんな消えてしまった。今でも彼らの、あるいはそのまた先人の好演を録画録音で親しむが、みんな鬼籍の人なので何度聴いていても変化はない。いや、変化がないからいいんだけど、少なくともぼくの落語耳に進歩はない。
やっぱり落語というのは、生もので、その席、その時代、その呼吸に出会うからこそ、面白味を超えた喜びがある。昔、談志師匠が沖縄開発庁長官をやめて寄席に戻り
「国会をしくじって帰ってきました」
これが大爆笑。今聞いても面白いエピソードだが、その場にいてこれを聴いた人たちの感じたおかしさといったら、無上のものだったに違いない。これは落語本編じゃなく芸人の了見が受けた件だが、こういう瞬間に出くわしたいと思うなら、やはり今の、現在進行形の落語を聞くべきだと思うのである。
そういうわけで、2020年10月15日、わがふるさとに「柳家小三治一門会」が来ると聞いた時は、こりゃあいかなきゃならないと思いました。
小三治師匠、御年80歳。当地には六年ぶりのお越しのこと。
長らく落語会に行ってなかったぼくだけど、なんだか胸騒ぎがしたので、チケットを取って観覧に出かけた。
不謹慎かもしれないけど、正直に言おう。
過去にどんだけ後悔したことか。
円楽、行けばよかったな。
米朝、行けばよかったな。
歌丸、行けばよかったな。
談志、行けばよかったな。
いつでも行ける、また来てくれると思っていたら……。
今見とかないと……。
拝んでおかないと……。
まるで出開帳である。
そういうわけで、人間国宝柳家小三治師匠とその一門会を観覧したので、ここにその記憶として書き留めておく。このブログに載せてる噺家は故人に限定していたが、今回に限って解除します。
柳家小三治に対する現今の期待値は高い。高いというのは、いまさら落語界を牽引して云々というのではなく、寄席や地方公演などにおける「さあ次は小三治師匠だ!」という熱気である。簡単に言っちゃうと客がミーハーなだけなんだが、それにしても今いるすべての落語家の中で知名度があり、かつ、レジェンド級を上げるとしたら、この方以外にいない。もちろんほかにも歴々の方はいる。馬風師匠、川柳師匠、遊三師匠……だけどやっぱり、いちばんは小三治師匠なのである。
なぜなのか。
やっぱり、テレビの力だと思う。
いまや「テレビに出ない落語家」の代表たる小三治師匠だが、昔は随分出ていたのを覚えている。その時に築いたものが今なお続いていて、集客になり、ブランドとなり、なにかこう、小三治師匠にしかかもせない世界を作っている。
逆に言うと、観てる側には常に「テレビに出てた人」「テレビの人気者」としてとらえる。小三治師匠がある時からあまりテレビに出なくなったのは、そういったフィルタがかかるのが嫌だったのだろうか。
小三治師匠をつかむのは難しい。
お出しになっているエッセーを読むと、結構気難しい人じゃなかろうか、と思う。枕を集めた感じのエッセーはそうでもないが、こと「落語家とは」とか「落語とは」という話になると、随分こう、ドライというか、つきはなしたというか、少なくとも他の芸人の本と違って、棘がある。
ぼくはこの棘に、苦節を感じずにいられない。
小三治師匠が入門した頃は、昭和の名人上手がまだ絢爛豪華な輝きを放っていた。志ん生・文楽・圓生・可楽、そして小さん。先輩のラインナップもすごい。志ん朝・談志・柳朝・円楽・円蔵。小三治師匠も17人抜きで真打になる力の持ち主だったが、彼らに向けられるスポットライトが強すぎて、どうも陰になることが多かったように思われる。
そんな中で小三治師匠はコツコツと芸を磨いた。時がたち、大師匠らが天に召されていく。先輩らは協会を飛び出したり、早世したり。
最後に残ったのが、小三治師匠だった。
名だたる師匠連や先輩格を抑え、人間国宝にまでなった。
この境遇は小さん師匠と一致しているように思う。彼もまた、先輩の志ん生・文楽らが死に、ライバル歌笑が死に、痴楽が脱落し、真打考査で対立した圓生が死に、トンガリが死に、スターの中で生き残り、人間国宝になった。
小三治も小さんも、ライバルたちよりちょっと年若だったことで生き残り、「最後の名人」となることができたように思う。生き残り&一人勝ち。まさに「長生きするのも芸のうち」だ。
もちろん芸も素晴らしい。柳の芸は、噺の持つおかしみを大切に、欲張ってあざとくしない芸風。何か面白いことをしてしまいたくなるところを、我意を抑えていくあたり、まさに辛抱、地道。
こんにちの小三治師匠を見ていて、ぼくはその苦節を勝手に感じている。インタビューやエッセーの小三治師匠は、ぼそぼそしゃべる見た目と裏腹に「どうだ!」と言っているような感じがする。何かこう、棘がチラ見えする。談志師匠が亡くなった時のインタビューなどは、積年の何かを感じずにいられなかった。
さて、一門会のレポートを。
わが故郷で行われた一門会では、小三治師匠は仲入り後一席の受け持ち、お決まりの長いまくらから『粗忽長屋』、「アンコールにお応えして」と(実際にカーテンコールがあったわけではない)『小言念仏』を演じた。
師匠はコロナ禍で長らく席が無く、こうして地方を回ることができて心底うれしそうだった。主催者に連れられて行った蕎麦屋を何度もべた褒めした。大変なコマーシャルである。箱は間引きの700人限定だったがライブ配信されていたので、お蕎麦屋さんったらお客殺到間違い無しである。
まくらの後は『粗忽長屋』。柳家一門のお家芸なので、出だしで「そこつだな」と思った瞬間に感動した(これもミーハーの範疇か)。
すごいなと思ったのは、客席がずーっと小爆発状態だったことだ。大爆発はさせず、笑いの小爆弾を絶えずはじけさせる。粗忽長屋という古典落語のすごさもあるけど、やはり国宝級の名人はすごい。客を疲れさせずに延々と笑わせる。
川柳師匠や先の円歌師匠など、大爆発型の三遊とは違うなあと、感心した。
お次は『小言念仏』。本来予定はなかったが、師匠はお客様の前で芸を披露できることがうれしすぎて、閉演時間を10分ほどオーバーすることを告知したうえで、これを演じた。
まさに小三治十八番。
名演・怪演、至芸・名人芸。
大いに笑わせていただいた。
ただ、そのせいで、前の『粗忽長屋』がかすんだのは間違いない。あまりにも小言念仏がよかった。
小言念仏を聞いて、小三治師匠は観察眼の人だと思った。ディテールとリアリティが見事で、きっと日常でも人の動きや世の流れをつぶさに見て、いろいろなことを考えておられるのではないかと思う。
キーとなるシチュエーションを引っ張って断続的に笑いにするのは、もう一つの十八番『花色木綿』でも同じである。
それらと比べ、ストーリーラインのある『粗忽長屋』などは、それはそれで素晴らしいのだが、やはり小三治さんが来るならストーリーものじゃないのを聞きたいな、という風に思われてしまうのも仕方がない。
最後の名人柳家小三治。
聴いてよかった小三治一門会。
前の三之助さん『浮世床』、一琴さん『牛ほめ』も良かった。
名人芸を記憶に焼き付けつつ、若い噺家さんも聞いていきたいところです。
ちなみに、今小三治さんをのぞいてレジェンドクラスで気になっている人は、二代目ブラック師匠です。が、こちらは地方にはいらっしゃらないだろうな。
おしまい。