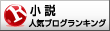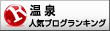コメディばかり書いていて思うことがある。
サッパリ売れねえ。
自分の不才は棚に上げ「もしかして、そもそもコメディというもの自体が人気無いんじゃないか?」とか思っちゃったりする。
よく考えたら、自分だって小説を買ったり映画を見たりする時に、敢えてコメディには手を伸ばさない。どちらかというと、「恋愛」「パニック」「SF」のように確固たるくくりになっているものばかりを選ぶ。それに、「コメディ」というのは、もしかしたら一つのジャンルではなく、ジャンルに付随する特徴をあらわす言葉なのかもしれない。「ラブコメ」「パニック&コメディ」「SFコメディ」のように。
なんだかんだいって、世の中には二の線、三の線ってものがある。それぞれ役割があって受け容れているのなら問題はないが、中には別に受け入れたわけではないのにそんな状況に陥り、不当に低い評価を受けてしまっているものもある。
今でこそ落語家がTVタレント化して差がないかもしれない。ところが往年の名人伝を紐解こうとすると、情報量に大差がある。江戸落語なら、志ん生・文楽・圓生・三木助・可楽と、すぐにいくつでも並べられるのに、上方の名人というと……
実際にはマダいるんだろう。しかし人口に膾炙するのはこのくらいじゃなかろうか。いや、ぶっちゃけ、「一人も知らない」って人もかなりいるだろう。
次の世代になってようやくご存知の顔が揃いだす。
上方落語はこの「上方四天王」によって再興されたといっていい。それ以前は滅亡寸前・風前のともしびと言われていた。評価も何もあったものじゃない。無くなりかけていたのだ。ゆえに往年の伝記が語り継がれていないのである。
そもそも落語の起源は、江戸初期の上方にあるといわれている。時代が巡って江戸にも発生し、それぞれ独自の変化を遂げた。商人の街と武家の膝元では、当然趣向が違った。上方落語は、個性的でアクの強い市民を相手する必要があっただけに、独特の傾向と癖を有した。そのため他の地域でなかなか受け入れられず、局所的にしか発展しえなかった。それが上方落語と江戸落語の差を生んでしまったのかもしれない。
上方落語全体の興隆について、書いていたらキリがない。今回は、私が個人的に「もっと高く評価されるべき」と思う上方噺家をピックアップしよう。
その噺家とは六代目笑福亭松鶴である。
上方四天王の中で最年長。下火だった上方落語を実父五代目と共にあの手この手で再興した。消えてしまいそうな噺を掘り起し、目鼻を付けて蘇生させたのは米朝師匠かもしれないが、落語雑誌や落語会を企画して業界そのものを築き直したのは松鶴師匠の功績だろう。
芸風は、一見大胆で豪快なようだが、実はきわめて繊細で、人物描写は細部に至るまで神経が通っている。
十八番は「らくだ」。松鶴と言えば「らくだ」、らくだと言えば「松鶴」と言われるほどである。江戸落語では志ん生や可楽が有名だ。私ははじめて松鶴の「らくだ」を聞いた時、そこで使われている上方言葉が分からなかった。
おう、らくだっ、らくだはおるかっ? はぁあ、どえらいどぶさりようを、さらしよッてからに。や? なんじゃ? こやつ、ごねてけつかる。
「どぶさる」「ごねる」…たぶん「寝る」「死ぬ」という意味だろう。TVやラジオ、地方落語会ではまず間違いなく通じない。しかし上方落語の歴史や文化を重んじるなら、この濁った音のニュアンスこそ本来の「らくだ」であり、正統なんだと思う。
ちなみにサゲの「ひや」も上方言葉だ。火葬場の事で、字を当てると「火屋」。江戸では「焼き場」(「黄金餅」などに登場する)。しかしどうしてこのネタに限っては江戸落語でも「ひや」なのだろう。掛け調の「冷や(酒)」をそこまで活かしたかったのだろうか? いっそ根本的に変えても良さそうな気がするが。
「らくだ」の他、松鶴師匠のネタというと…
- 夢八
「じんべはーん、じんべはーん」と悲痛な声が耳に残る。化け猫は出る、首つりは出る、だのに可笑しい名調子。 - 次の御用日
「ア゛ア゛ア゛」で埋め尽くされるお白洲は爆笑必至。しかしその背後に、恐怖で口が利けなくなったお嬢がいると思うと、恐ろしい噺である。 - 初天神
お祭りに行く父と子のやりとり。松鶴師匠は子供を演じたらピカイチ。三代金馬しかり、声が野太い人は子供に向いているのだろうか。最近様々な噺家がTVで演じて人気の高いネタだが、松鶴師匠以上の初天神は見たことが無い。
しばしば「米朝は上方落語をかみ砕いて全国に通用する落語にした」「松鶴の落語こそ、本来の上方落語」と言われる。どっちが良いとか悪いとかではないし、功績もそれぞれである。確かに、大衆に対する上方落語へのいざない役は、米朝や枝雀が担ったといえる。しかし上方落語をそれ以上に深めて聞きたいと思うと、やはり松鶴師匠の系統にお出ましをいただきたくなる。だが、今いったい誰がそのポジションにあるのだろう。
昨年三代目桂春團治が没し、上方四天王はみな天に召された。
もしかしたら上方落語は、近いうちにもう一度頑張らないといけない時がくるかもしれない。
*
落語のネタは上方発祥のものが多いんです。良いものは場所を問わない、良ければどんどん伝播していくってことです。
でも、小説の場合、特定ジャンルのファン層ってのは、やっぱりあるでしょうねえ。
以下「コメディ」というより、「学園モノ」と「プロレスもの」のご紹介です。

- 作者: 小林アヲイ
- 出版社/メーカー: さくらノベルス
- 発売日: 2017/12/25
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る