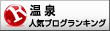※長さ:400字原稿用紙換算約10枚。
今回はちょっと思い出を書いてみようと思う。
O村先生に初めてお会いしたのは、2012年の夏ごろである。ちょうどその頃、ぼくは急に独り暮らしをすることになり、時間を持て余してネットを視ていたところ、地元に文学サロンがあることを知った。それまでしばらく文学どころではなかったので、自分の時間を取り戻そうと、何にも迷わずに入り込んだ。
そこにたまたまいらしたのがO村先生である。O村先生は小柄なおばあちゃまである。お召し物やお化粧、たたずまいは、先生が長らく美容に従事されていたと知れば、大いに納得するところである。知性と気品が漂っている。強い目力を感じる。先生はサロンの利用者で、運営者とも懇意であったようだ。
先生は初対面のぼくに、とうとうとご自身の過去を語られた。戦争のこと、お仕事のこと、ご家族のこと そして、ご自身が65歳で文学をお始めになったこと。すでに傘寿をお過ぎの先生は、年齢よりずっとお若く感じた。見た目や仕草以外に、とにかく熱が、パッションがすごい。先生はわずか三年前に地元文学賞をお獲りになられていた。ぼくは自己紹介程度に「自分も小説を書いたりするのが好きですよ」と言った。すると、
「あんたも(地元の)文学賞に出しなさい」
強くお勧めになる。ぼくは苦しげにほほ笑んだ。ぼくは文学賞というものについて、当時も今も大した重さを感じていないのだが……35歳のぼくは熱気に圧倒されて、返事もできない。先生の「ガッツ」「負けん気」「求道心」に食われていたのだ。
その文学サロンは、小説を書く人を集めて合評会のようなことをやっていた。まもなくそれは無くなったが、無理もあるまい。そもそもああいうものは共通の目標を持つ人たちが集まって価値観を一つにしてやってくものだと思う。でないと、たんなる好き嫌いの意見交換になり、喧嘩になるのが関の山。実際当サロンでもそういうシーンは散見されたらしい。まあ、文学サロンと銘打って集まりが結成された以上、そういった場を設けておかなくては看板に関わるようなことから、やったのかもしれない。
ある時、そこで私の作品が俎上にのった。誰からも大した声はあがらなかった。O村先生は難しい顔をして、「別の作品を読ませなさい」と仰られた。ぼくは戸惑ったが、人生の大先輩の仰せでもあることだし、お渡しした のだと思う。もしくは郵送したか。その辺はちょっと覚えていない。紙に刷った50枚くらいの原稿。『贋物』という題である。
しかしそれ以来、先生にお会いする機会が無くなった。文学サロンと距離ができた 別に仲違いをしたわけではないけど、なんとなく足が遠のいた。その後、合評会は霧消したらしいと噂を聞いた。つまりお会いする場自体がなくなったのである。
けれども O村先生に送った原稿は返送されてきた。なんだか送った時より随分厚みを帯びた封書。封を切って中身を取り出す それは、はしっこがくしゃくしゃになるほど何度ももみほだされた、ぼくの原稿だった。おびただしい赤が入っている。全紙ほとんど真っ赤。赤々赤。書ききれない注意書きは紙の後ろに小さな字でビッシリ書き込まれている。ぼくはそれを全部読んで「あっ」と思った。大きな気付きがあった。それがあるから今があると思う。文末にはエールがあった。きびしさとやさしさが溢れていて、同じ書くもの同士、ということを強く感じさせる応援であった。
すぐにお礼の電話をした。
「あんた、作品を書いて文学賞に出しなさいよ」
と言われた。
「出す意味が分かりません」と答えた。そしたら
「書き続けるんだよ」
と。それには「もちろん」と答えた。
それっきり先生とご縁が途絶え、何度か季節が廻った。サロンに出入りするようになってから仲良くしてくださるN田さん。この人はぼくの大好きな人で、しばしばお酒をご一緒させていただく。年齢的に大先輩で、文学のキャリアも果てしなく違うこの方から、時折O村先生のお噂を伺った。いろいろ体調があれらしい、と。お年もお年だから、と思ったりした。それでも先生の強さみたいなのを思い出すと、まだまだ大丈夫、鋭意執筆中のはず、と思った。願うように思った。
その後、2019年。春。ぼくが禁を破って投稿した小説が、地元文学賞で最終選考に残り、で、ぽしゃった。O村先生はN田さんからそれを知り、お電話をくださった。
「あんた、惜しかったね! でも、残るだけでもたいしたものだよ!」
七年ぶりにお声を聞いた。先生の声はきらきらしていた。
先生はぼくの作品が残ったと知り、わざわざ新聞社に言って原稿を取り寄せ、何度も読んで、言うことをまとめて、お電話をくださったとのことである。手が悪くて赤を入れられないから、直接伝えようとお考えになられたのだと思う。
それから約二時間、あそこがああで、ここがこうで、それで、こうで……。電話口の特別講座。先生は全く疲れを知らない強い口調だった。そして「秘中の秘」を教えてくださった。ぼくはまだその必殺技を使うほどの筆力を持たないのでふところにしまったきりだが、ずっと忘れないでいようと思う。
先生はひと通り講義を終えると、最後に
「また(地元)文学賞に出しなさいよ」
とお言いつけになった。
ぼくはわざわざお電話くださった大先輩にさすがに「そんなの無意味だ」と言えず「いえいえ」と言葉を濁した。
「一度最終に残ると、次に有利だよ」
「じゃあ次は、地元じゃなくて全国の賞に出します」と言い逃げる。すると
「馬鹿を言いなさんな。まずは地元、次に九州、そして全国を目指しなさい」
まるで戦国時代の島津家のような天下統一のシナリオをお示しになられた。やっぱり先生は違う。
こんな交流は、ぼくにとって非常に貴重である。
ぼくには師匠はいない。憧れの作家もいない。むしろ居てはいけないくらいに思っている。小説は自分の都合で書いているのであって、憧れをなぞってる時間はぼくにはない。また、上手に書く必要もない。作為はあとから読み返して嫌味に感じるからだ。
それでもぼくにとってO村先生は、数少ない貴重な道しるべである。
O村先生にはお弟子がたくさんおられる。地元鹿児島を中心に、いろんな文学賞が出ている。先生のおっしゃるには、朝起きて新聞受けをみると原稿を突っ込んでいる弟子がいる。お弟子がやってきて投稿前の作品をチェックを求めたりする。それだけしてみんな先生の教えを乞いにやってくる。
なのに、ぼくなんぞはまったく不遜な態度で、電話もいただく一方で、言われてしぶしぶ原稿を送る(しかもお持ちするのではなく郵送!)。われながら生意気な若造だと思う。
しかし…誰に何を言われようと引けない部分もある。文学賞は嫌いだし、ましてや他人の手の一ミリでも入った原稿を自分の名前で投稿するなんぞ、いかがなものかと思う。そんなものはもう自分の作品じゃない(Amazonに出している『贋物』は先生の赤を全く反映させていない)。
一度そのことを先生に正直に言ったことがある。そしたら「分かる」と。「だから私も無理には言わない」と。先生は文章を書くだけでなく、書く人の気持ちも しかもいろんなタイプの物書きがいることを 許容し、理解しておられるのだと思った。
それはすごいことだと思う。
なかなかいないと思う。
そんな方が、不遜な若造の襟首を捕まえてわざわざ指導してくださるのだ。ありがたがらないとバチがあたるだろう。バチは怖い。
あと、それでなくても、O村先生そのものが、ぼくにとって興味津々である。だから、従う従わないは別にして、先生のお言葉には全て耳を傾けたい。
先生には、実地に教えをいただき、本当に感謝しています。また、文章書きがどういう矜持で作品に向かうべきか、教わりました。先生の後ろ姿にそれを見せていただきました。多くのお弟子さんが先生の弟子であることを誇りに感じていると思います。ぼくは、正規の弟子じゃないけれど、隠れて師匠だと思っていこうと思います。
*
*
*
で。
このたび先生の米寿のお祝いがありました。
八年ぶりにお会いしました。
「あんた太ったね」と言われました。
へこみましたが、正解。前にお会いした時より増7キロです。
「先生おめでとう」と申し上げたいだけだったのに、逆に「あんたの小説は冒頭部分がまずい」「あれがだめ」「これもダメ」といろいろとご指導いただきました。
ほんとお元気です。
勝てませんや^^;