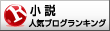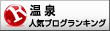今年ウン歳になる。
……まあ、何歳でもいいでしょう。
ついては区切りの年だというんで、同窓会のご案内をたくさんいただく。知らない間に中学校の同窓生のライングループに混ぜられて、しょっちゅう何らかのメッセージが飛んでくる。着信音がまことやかましい。あんまり絡みたくない私は未読スルーだ。
そうはいっても、たまに懐かしい友達の名前を見つけると「おお」と思ったりする。女子は名字がかわって分からない そんな中、一人の女子のメッセージが印象深かった。その人は名字が変わっていなかったので、すぐ思い出せた。ラインの流れを見ていると、いかにも特徴的・傾向的だった。
「明日東京でーす。会える人いない?」
「〇〇君ありがと。会お!楽しみ」
「友達も連れて来たりしない?」
「来週帰郷します。××子久々に女子会しよ」
「友だち連れてきます。××も友ありOKで」
「え~連れてきてよ。一人でもいいから」
「話するだけだよ」
「えー。〇〇君も知ってるよ」
「怪しくないって。ウチもしてるし」
「大丈夫だってば」
「再来週大阪でーす。同郷いる?」
あああ。推して知るべし、だ。きっとア〇ウェイみたいな何かに決まってる。
同窓生たちよ、頼むから印鑑なんか持っていくんじゃないぞ。
この女子のことは、よく覚えている。成績優秀。常に上位五人に入っていた。色白でソコソコ可愛らしく、控えめで、休み時間はいつも読書をしている。口数が少なく、友だちは女子だけほんの数人。男子とは接点も無かったんじゃなかろうか。とにかく、クラスに限らず学年全体で寡黙で可憐な優等生で通っていた。
何が彼女をこうも変えたのか 。
卒業後の人生がどんなだったのか知らないので、そんなこと分かりゃしない。でも、源流はやはり育った環境に求められると思う。そして大筋は定石通りの変化をたどるものだ。
そう、地味な優等生は、たいがいロクな大人にならない。
これは私が勝手に定めた人間の法則シリーズの「『感謝々々』とのべつ言ってる奴に大したヤツはいない」に並ぶ大原理である。
優等生には優等生の孤独がある。性格が真面目で控えめならなおさらだ。私の中で古今亭志ん朝はまさにそのイメージの噺家である。
親父が大名人の聞こえ高い五代古今亭志ん生。二世のプレッシャーたるや、相当なものだっただろう。しかも親父は他人に真似できない天衣無縫の芸風。同じ事をやっても絶対勝てない。
そこで身に刻みこんだ落語は、三代金馬の歯切れの良さ、八代文楽の明るさ、六代圓生のクサさ(良い意味)...追及しうる限りの落語を徹底的に修めていった結果、志ん朝の落語は、他のあらゆる名人のエッセンスが詰め込まれ、いかにも贅沢で豪華絢爛な芸風となった。
わずか五年で真打昇進。36人抜きという大抜擢である。五代談志、五代圓楽、五代柳朝(のちに円蔵)と共に「落語四天王」と並び評された。芸はどう見ても志ん朝が図抜けて上手かった。しばしば「最後の名人」と称される。彼の没後、肩を並べたと言えるほどの噺家は出ていないのは確かのような気がする。
しかし…
志ん朝以外の四天王は、何かと印象が強い。早世した柳朝はさておき、
志ん朝にはこういったものがない。
談志も圓楽も芸では志ん朝には敵わなかったと思う。けれどもこの二人はそれぞれの立場から落語について背負うものがあったので、それがおのずと芸に厚みを持たせ、スケールの大きい落語になった。
だが真面目な優等生、古今亭志ん朝は ああ、何と言えばいいのか 光が当たりきらなかった。落語協会分裂あたりからミソが付いた気がする。え? 住吉踊り? ウーン…。
晩年は、芸についても不安を感じさせた。病気をして徐々に体力がなくなっていく。それでも志ん朝は、ポーズに挟む「ェエッ?」「ォオウ?」を若い時と同じように使い、昔と変わらぬテンションで演っていた。
この芸風、年を取っても同じようにできるのか…?
談志は志ん朝の死後、インタビューでそのことに触れ、「いい時期に死んだ」とさえ言った。死んですぐそれを言っちゃうのが談志の談志たるところだが、全くその通りだと思ったものだ。
世情に掉さす芸人として、伝統芸を担う落語家として 。
志ん朝は真面目な優等生ゆえに、どこか慎重で融通が利かず*1、思ったほど拡がりきらなかった。むろん、芸道三昧が本望なら、本人は最高の人生だったかもしれない。しかしオーディエンスとしては、もっと幅広いものが観たかった。戦後馬鹿売れした圓歌と三平は、トコトン芸人だった。かたや志ん朝は職人芸だった。
いろいろな名人上手のエッセンスを取り入れただけに、志ん朝の持ちネタは多い。思いつくものをざっと紐解くと
二番煎じ/黄金餅/火焔太鼓/寝床/搗屋幸兵衛/そば清/付き馬/大工調べ...
居残り佐平次/小言幸兵衛/百年目/百川...
分かる人には分かるだろう。上は親父譲りの古今亭の芸。中段が黒門町、下段が柏木だ。
珠玉は「二番煎じ」。「火焔太鼓」もいい。この他にも名人伝「宋珉の滝」「抜け雀」「浜野矩隨」など、聴かせる噺もいい。おそらく声が、長く聴いていて耳に心地よいからだと思う。しかし、「ちきり伊勢屋」「文七元結」など一部の長講物は、六代圓生、八代正蔵と聞き比べるとやや聴き劣る。ちなみに文七元結については、談志が非常に良い。
*
志ん朝師匠の芸を聴いていると、パリッとした感じが心地よく、落語を聴く喜びを教えてくれます。ちょっと今回は批判的な論になっちゃったけど、やはり私は、志ん朝落語が大好きです。
同窓会は、こわいから止しとくことにします。
*1:だいたい、死ぬまで鰻断ちするなんてエピソードも、生真面目の極地をよくあらわしている。豪邸を建てたり外車を乗り回すなんてのも、真面目な人間の典型的な反動パターン。いわゆる「〇〇デビュー」的なものではなかろうか。