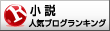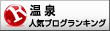普段、生身の人間と話す機会がほとんどない。そんな状況で日々動画共有サイトなどの落語ばかり視聴しているから、私の耳に入ってくる人間の声は9割9分は落語家の声である。それもほとんど鬼籍の人。おまけに、こういうブログを誰が読むともなく、金になるわけでもなく、たたただ純粋に好きだという一心から書いているわけで、私の脳みそはまるっきり落語オタクなのである。
そんなだからごく稀に人に会っても、ついつい落語の話をしてしまう。いや、落語そのものの話をしなくても、自然と落語用語を比喩や引用で使ってしまう。
あいつらはゲンベエさんにタスケさんだからなあ。
え? ぼく? もう一杯ビールが怖い。
んでさ、その時の道中の、陽気なことォ♪
これはもう病気だ。
ちなみに、上記の元ネタが分かる人がいたら病気の可能性は多少あるけれども、この程度じゃまだ全然軽症なので、もっと落語を聴きなさい。
私の友人はみなとてもとてもいい人たちばかりなので、私が落語好きであることを知ると、興味を示して(社交辞令なのかもしれないが)こんなことを尋ねてくれる。
ねえねえ、落語って、誰のを聴いたら面白い?
女性からこんなことを言われたら、求婚されたかと思うくらい喜ぶ。といって男から聞かれても、別に悪くは思わんぞ。
この質問、実は非常に難しい。今の噺家で挙げるか、私が好きな噺家(鬼籍込み)で挙げるか。ただただ笑えるものを挙げるか、落語芸として秀逸なものを挙げるか。落語布教のチャンスである。失敗は許されない。誤ってその人に遇わないものを教えて「つまんねえ」とか思われたら最悪だ。きっとその人はまた別の人に「アイツが落語面白いって言うから聴いたけど、時間の無駄だった」などと言いふらすだろう。悪い噂は良い噂よりずっと早く広まるという。嗚呼、この苦悩はおそらく、BLを布教する腐女子における伝導の困難さに通じるものがあるだろう。
初心者に分かりやすく、聴きやすく、面白く、なおかつ「ほかの噺も聴いてみたい」と思わせる落語家とは 。いろいろ考えた結果、私は三代目の三遊亭金馬師匠こそその役にふさわしいと思う。
野太い声ながら表現豊か。調子はなめらかで卒がなく、噛むことなんてほとんどない。元は講釈師だったそうだが、雰囲気がおかしいからお客がどうしても笑ってしまい、勧められて落語に転向、初代円歌に入門したという。
リズムがあって知性もあって、飾らない可笑しさがある。実際、数多くの随筆を残し、エッセイストとしても優れている。見た目のインパクトもすごい。つるっつるのやかん頭に出っ歯。一度見たら忘れられない濃さがある。一名「やかん先生」。
演じるのはほとんど古典落語だが、新作も多く、秀作ぞろいだ。ぜひ聞いてもらいたいのは金馬の最大の当たりネタ「居酒屋」である。耳に残るのは、小僧さんの御品書の読み上げだ。
できますものは、つゆ、はしら、たらこぶ、あんこうのようなもの。ぶりにお芋に酢だこでございます。ふぃいぃぃぃ。
セリフを調子よく諳んじることにかけてはこの師匠を超えられる噺家はあるまい。耳に馴染んで心地の良い口調は、さすがは講談出身である。
孝行糖の本来は、うるのこごめにかんざらし、かやにぎんなん、にっきにちょうじ、チャンチキチ、スケテンテン(孝行糖)
古い蜀山の歌に「まだアオい、シロ(う)と浄瑠璃、クロがって、アカい顔して、キな声をだし」なんて川柳がございます(寝床)
その他にぜひ聞いていただきたいのは「勉強」「真田小僧」「高田馬場」など、枚挙にいとまがない。人情話では「藪入り」も秀逸だ。
そういえば、自分のやかん頭を見せてしばしばこんなことを。
まだわたくしの頭に緑の黒髪はなやかなりし頃 どうぞ、そう緊張なさらずに。
客がどっと笑う。客席の空気を見事にコントロールする自虐のフレーズにも,ひとつかみの知性が漂う。六代圓生も大山詣りで自分の薄毛を笑いにする録音があるが、大看板の自虐ネタは反則級の弛緩術である。
私は大好きだし、事実誰が聞いても楽しくなれる金馬師匠なのに、往年の落語界での評判はあまり芳しくなかったようだ。当時の落語評論家は金馬の落語を俗っぽすぎるとしてこきおろした。トリで金馬が上がったら嫌な顔をして帰ったという。また、志ん生・圓生は金馬とリレー落語を演って「ひどい目に遭った」とこぼしたそうだ。
評論家も両師匠も、何がそんなにいやだったのか。
金馬は途中から東宝専属になり、寄席には出ることができず、半ば孤高の落語家となる。それでいて往時もっとも売れた落語家だったから、おそらくやっかみみたいなものもあったのだろう。また、落語そのものも、活躍の場が普通の落語家よりラジオやレコードの割合が多いために、抑揚や声音に寄るところが大きく、演り方がオリジナル化しているところがあったのかもしれない。
けれども、桂文楽はとある落語会の顔付けを見て「なんで金馬さんがいないの」とメンツに疑問を呈したと言うし、志ん朝・談志は金馬を大きく評価している。事実、古い人に尋ねれば、金馬落語で落語好きになったという人は多い。あの調子のよさ、鮮やかさを聴いて、落語なんて不愉快だと云う人はいないだろう。
しばしば桂文楽を「きれいごと」「楷書の芸」などと評するが、この人もまた同様である。両者とも三代三遊亭圓馬(橋本川柳)の薫陶を受けたというから、圓馬師にそのルーツがあるのだろう。確かに両者には圓馬師に通じる口跡がある。
*
最近、落語がますます流行っているようです。
これは、とある噺家さんに直に聞いたのですが、落語は流行るとダメになるんだそうです。というのは、寄席の客が甘くなって、演る側の芸どころが鈍るんだとか。たしかにホール落語一辺倒の流派はクサイですもんねェ。
実は落語の入り口って難しいのです。
中年世代の自称落語好きに尋ねると「桂枝雀から聴きはじめた」って人、多いんですが、この人たちも結局枝雀から広がらない。枝雀ファンで停まっちゃってる。彼があまりに面白すぎるから と同時に、彼はすでに古典芸能としての落語からだいぶ離れていました。そこ行くと、談志ファンはきちんと古典落語に流れていきましたね。さすが家元だ。だいぶ改作されましたけど。
もしこれから落語を聴いてみたいなという方には、ぜひ金馬師匠を聴いて欲しいです。落語耳の基礎となること間違いなし。噺家に限らず、ネタのみならず、落語そのものがスッと入ってきますから。
以上です。