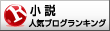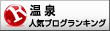11.29 @鹿児島県民交流センター
コロナウィルスで一度延期になったものの万を持して開催です。
九州プロレス……名前は聞いたことがありましたが、実際に見るのは初めてでした。
正直、見たかったのは藤波辰爾選手です。
実際に興行がはじまってみると、どの試合も、どの選手も、非常に個性が際立っていて、面白かった。興行全体の緩急の付け方は、下手な全国区の団体よりも見事だったと思います。
藤波選手を見ることができて良かった。そして、この団体を知ることができて良かった。今後の楽しみが増えた気がしました。
ローカルプロレスは、なかなか素晴らしいものです。明るい未来があるような気がします。
プロレスは、2010年代前半から長い低迷を迎えました。その中で一部の小団体は、生き残るために地方特化を画策、新たな市場を模索しはじめました。どの団体も経営的に逼迫しながら、興行を続けてきました。
月日が流れ、2020年現在、プロレスブームはメジャー団体の強い牽引力で息を吹き返した というより、新たに生まれ変わった感があります。
しかし古くから見ているファンにしてみると、新興のプロレスは、まるっきり違うものを見せられている感じが否めません。派手な技とパフォーマンスが主流で、それはそれで素晴らしいエンターテインメントですが、かつてリングの日常だった重苦しい息遣いは無く、ぼくが知ってるプロレスは影走る走馬灯となってしまったようです。
郷愁を覚えつつ、ふと地方プロレスに目を向けると、小団体ならではのお遊び的な見せ場はありますが、意外や意外、そこにはかつて見たプロレスの幻影が、わずかながら残っているような気がします。地方特化して本流を離れた小団体たちは、往年のプロレスの法灯を携えたまま、日本の各地に根付いていたのでしょう。何とも奇特なことです。
日本のプロレスは、力道山が日本に持ち込んで以来、ガラパゴス的進化を遂げてきました。それがこんにち、日本各地に勃興したローカルプロレスを見ると、奇しくも力道山が持ち込んだ当時のアメリカのスタイル、すなわちテリトリー毎に行われていた興行形式に似通ってきている……実に不思議な感じがします。将来、日本のローカルプロレス団体同士がカルテルを組み、NWAのような大きなマーケットになる未来も面白いかも知れませんね。