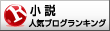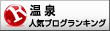とにかく落語が好きで、ひんぱんに聞いたり読んだり、記事を捏ね上げたりしていると、たまにこんな風なことを言われる。
ねえ、落語演ってよ。
いくら好きでもできねえよw
あるいは合コンなど人の集まる席で誰かが私を紹介する際
こちらアヲイさん、落語家で~す。
おいおいw違うぞ違うから。
知り合い同士なら「落語好き=落語の話ばかりする=落語家」みたいな冗談めかした言い方は通用するだろう。けど、合コンなど初対面の席で言われると、相手は信じかねないではないか。最近、落語はなぜだかブームだし、同じ年齢の咄家もたくさんいる(もっとも、そうやって私を陥れようという知り合いの戦略かもしれないが)。
落語なんて、ホントできるものではない。
私はいつもこのブログで、語り継がれる大ネタや大名人たちの文句ばかり言っているが、プロの噺家さんはやっぱりスゴイと思う。尊敬する。
噺を覚える記憶力、人前で芸をする度胸。息や仕方の創意工夫 芸道は複雑な一本道である。とても真似などできない。
ごくたまに、宴会芸的に落語をやるオッサンがいる。会社の忘年会などで披露しているのだ。見ていると「へえー」「ほおー」という感じがして、周りは
なるほど、覚えりゃ誰でもできるのか。
と勘違いしがちだ。
だが! 私としては、落語研究を重ねれば重ねるほど、落語というものがいかに難しい物か分かってきて、知れば知るほど出来やしない。宴会芸のオッサンは、その難しさを知らないから、無邪気にやれるのである(ウケは別として)。
なぜ私がこれほどまでに「真似できねェ」を強調するのか。
その理由は ごく単純。
覚えようと思って、練習したことがあるのである。
全然できない。超むずかしい。
別に本職のように大ネタをガンガンやれるようになりたいと考えたわけじゃない。前述のように、「何か演ってよ」と言われた時、全然応えないよりは、ちょっとした小噺でもできた方が、相手はせっかく気を遣って言ってくれてるのかもしれないから、いいと思ったのだ。
ま、あくまで小噺。軽く「演ってよ」と言って、いきなり文七元結なんか演られても相手は困るだろうし、こっちだって出来やしない。
小噺はいろいろある。
古典では「頭山」が有名だ。
頭山(志ん生):
ケチな人がサクランボの種を捨てるのがもったいなくて飲み込んだら頭から桜の木が生えてきた。あまりに見事に咲いたので、人々がケチの頭に群がって花見をしはじめる。ケチはうるさくてたまらないから頭の桜を引き抜いた。すると後に出来た穴に水がたまり、きれいな池に。舟遊びやら花火やら、また人が群がる。ケチはイライラしてその池に飛び込み自殺した。
この噺はショートフィルム化されて外国の賞をもらってた気がする。シュールで面白いのだが、誰にでも受けそうでは無いし、クスって感じじゃない。
桝落とし(志ん生):
昔は桝で罠を作ってネズミを捕った。
ネズミがきたら桝がパカッと落ちて捕まえる。
「おう! いま桝でネズミを獲ったぞ。大きいぞ!」
「桝の端から尻尾が出てら。大きくねえよ。小せえ」
「大きいやい!」
「小せえ!」
「大きい!」
「小せえ!」
すると桝の中からネズミが
「チュー」
志ん生師匠の小噺は、独特のゆるい口調「へぇ~……てぇのは、……ですから、へぇ~とォ~……」これだから面白い。天衣無縫の至芸、真似は無理。
かたや「江戸の鰹」黒門町の小噺は
ことしゃみせん(文楽):
田舎過ぎて鏡というものを知らない郷の男連中が浅草見物。鏡屋の看板「かゝみや」を見て
「かかみや?」
「嬶(かか)ァ見せる店か?」
店を覗くと綺麗な看板娘。
「えれえきれいな嬶ァだな…村のモンに教えっぺ」
一行は存分に鼻の下を伸ばして帰郷。仲間に言う。翌年仲間らが浅草見物へ。
「嬶ァ見せる店があるって聞いてたが」
ところが、この一年の間に鏡屋は無くなり、後は三味線と琴の店になっていた。
「ここらと聞いたが、かゝみやなんてないぞ?」
「おい、今年はやってないみたいだ」
「どうしてだ?」
「看板を見ろ。『ことしゃみせん』としてある」
ま、ダジャレで面白いんだけど、なんかねえ。田舎言葉とか、男の業というか。素材があんまりきれいじゃない。
桂文楽は小噺まで楷書の芸だ。こんなのもある。
コイが高い(文楽):
泥棒の大将が子分らを引き連れ、今夜の標的、料理屋の前に辿り着く。
「こんな店、俺一人で十分だ。おめえらは待ってろ」
大将、料理人の寝床に侵入し、だんびらを喉につけ
「おきろ、百両をよこせ」
料理人はびっくりしたが、命は大事と百両渡す。
「素直なやつ。ところで俺は腹が減った。お前料理人だろ。何か食わせろ」
「時化で魚がありません。できるのは鯉の刺身と鯉コクでございます」
「いいぞ」
「しかし大将。あなたは人から物を盗るのが商売。私共は料理を提供するのが商売。商ったものには対価を頂戴します」
「おう。払ってやるぞ」
料理人、料理をこさえる。大将、あっという間にたいらげ
「美味かったぞ。いくらだ」
「百両でございます」
「なに? 高いな。しかし……約束だ。ほれ」
大将、獲ったばかりの百両を払い、やれやれと表に出る。待ち受けていた子分らが勢い込んで尋ねる。
「大将、中の首尾は?」
「シーッ。……コイが高い」
江戸訛りだと「こえ」が「こい」になる。すなわち、「声」と「鯉」が掛かっている。面白いんだけど、訛りに理解が無いとなんのこっちゃか。それにしても文楽は駄洒落小噺が多いなあ。
「こえ・こい」については、自分でも小噺をこさえたことがある。
コイに落ちる(アヲイ作):
田んぼのあぜ道を歩くのは、年頃の高校生カップル。
男子生徒と女子高生。触れ合う指と、指の先。
その時、一陣のつむじ風が吹き 。
こうして二人はコイに落ちた。
これはつまり「恋」と「肥え」が掛かっている。田んぼ脇の肥え溜めに落っこちたってことさ。いわゆるクサい仲。御粗末。
談志師匠はまるでコレクションしているかのようにたくさんの小噺を持っている。まくらとして使う感じじゃない。
「ええ、小噺を少々……」
いつもこんな感じで唐突に入る。洋の東西を問わず、かなりのラインナップだ。心底小噺を愛しているのが分かる。
ご婦人が犬を連れて散歩している。男が見て
「おや珍しい、ブタを連れてお散歩ですか?」
「何言ってるんです? これは犬ですよ?」
「今私は犬に話しかけたつもりだったんですがね」
「そっちかよ!?」一人語りゆえに効く噺。類似したのに伯爵夫人の噺もある。
次は私の大好きな談志小噺。
「車掌さん、次の駅はトイレがありますか?」
「あります」
「お弁当は売ってますか?」
「売ってます」
「お茶は?」
「あります」
「週刊誌は?」
「あります」
「何分停車ですか?」
「通過です」
うーん。書いたって面白くないな。耳で聞いた時の最後のストンと落ちる感じはすごくいい。リズムが大事。
最後に「桜鯛」をご紹介しよう。
なぜ最後にもってきたかというと、この噺こそ、私が覚えようと思って練習したネタだからだ。
桜鯛(圓生):
昔、大名の食事には必ず鯛がついた。殿様は飽きていて、いつも片面に一箸付けたらおしまいだ。
ある春の日の昼食。殿様は城の庭の眺めながら食べている。そばにはご家老がついている。
「これ、今日の鯛はよいな。かわりをもて」
びっくりしたのはご家老。いつも食べないから代わりなど用意が無い。一計案じ、
「殿、庭の桜が見事でございます」
「なに?」
殿様が庭の桜に目を遣った隙に、鯛の表裏をひっくり返した。
「殿、ご所望の鯛でございます」
「おお、早かったな」
よろこんで食べる殿様。やがて
「うまかった。もうひとつ代わりを持て」
さあ困ったご家老。もうひっくり返せない。ウーンと悩んでいると、殿様
「もう一度桜を見ようか?」
家老の機転、展開の緊迫感、最後の殿様の粋なセリフ。この三つが混然一体となっていて、小噺の割に実に豊かである。
いわゆる大名小噺というのは、このほかにもいろいろあって、そのほとんどが「目黒のさんま」「盃の殿様」「妾馬」「蕎麦の殿様」など、大名ネタのまくらに来ることが多い。基本は殿様や家老が面食らう噺で、本ネタ前に観客に大名世界の予備知識*1を与える役割を担っている。だからそもそも大名小噺そのものを単独で成立させるのは難しく、私はスッパリ諦めた。
そもそもどうして私がこの噺にフォーカスしたか。
それは、六代目三遊亭圓生の最後の高座に由来する。習志野での催し。体調不良のため小噺で降りることをお客様に事前に断っての一席だった。その時のネタが桜鯛だ。
安直な私はこの話を聞いてこう思った。
桜鯛は、一席分もつ小噺なのかぁ 。
まったくもって、素人の浅はかさである。
ちなみに、この噺は何度口先で練習しても、しゃべれた感じがしなかった。セリフは覚えられても、身につかない感じ。やはりちゃんと師匠につかなきゃだめですね。
きっとこの記事を本職や研究家の人が見たら、「あったりまえだ、べらぼうめ」とお怒りになるかもしれない。「出来るもんか」「出来たと思ったところで、悪い癖だらけで聞けたもんじゃないぞ」なんて言われたら、ごもっともだ。
けれども、下手なりにチャレンジしたことは、かなり勉強になった。三遊・柳・桂での微妙な芸風の違い、登場人物の描き分け、酒飲みの酔い加減の段階的な仕方……おおっと、これじゃ桜鯛以外にもいろいろ練習してたことがバレそうだ。
とにかく、聴いているだけでは分からない難しさが次から次へと体感できた。耳専門の人も、ものは試しで体験されることをお勧めする。もうね、驚いちゃうから。
落語家はかくも複雑なことを一人でやっているのだと思うと、感嘆極まる。私が拙い練習で演っていると、噺を進めるうちにだんだん余裕がなくなってきて、いつもいわゆる熱演というか、気負いまくった状態になってしまった。これを超えるには、やはり人前に出て芸をさらけ、場数を踏まないといけないんだろうなあ。
落語はたかが落語なんてもんじゃない。
まさに、芸ですよ。
*
新作を、ちょぼちょぼ書いています。が、ゆっくりです。まあ誰も待っていないから、構わないよね。夏が終わるまでには抜けたい。あ、以下無料キャンペーン実施中。

- 作者: アヲイ
- 出版社/メーカー: さくらノベルス
- 発売日: 2015/05/24
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る