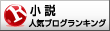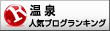いまさらながら、無責任姉妹3・4巻の合体本を出した。

- 作者: アヲイ
- 発売日: 2017/02/10
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
ついこの前、各所に御免を蒙ってシリーズ全作をアマゾン一極集中、KDPセレクトに登録しキンドルアンリミテッド対応にしたばかりである。合体本のリリースは、全品がKU対応である以上、KUの利用者に大きな意味は無い。出す側にしても、ランキングを気にするならむしろ合体版なんかない方がいいのである。
それでも出したのは何故か。
うーん。自分でも分からない。
ただ、ひとつ言えることは「何かしてみたかった」 それだけである。別に大それた野心を抱いているわけではないけれど、アカウント画面の折れ線グラフがほとんど動かないという閉塞感を打破するために、何かせずにいられなかった。あと、どうせ売れないのなら、安価でいいからできるだけ多くの人に読んでもらいたいという思いもある。
あ。
今うかつに閉塞感なんて言葉を用いたが、これはまさしくブーメランのように自分に返ってくる言葉だった。
だったら物語を書けよ。それが本懐だろ。
自分もまったくそう思う。書くのが好きなら、自分の道だと思うなら、そっちに邁進すればいい。一度公開した作品なんて、よほどのことがない限り振り返る必要は無い。いまのいま沸き立つ想いを、ただひたすら新しい原稿用紙に綴ればよいのだ。
だが、それができないから、本の表紙をいじったり、売り場の設定をいじったりする。閉塞感はあるけれど、沸き立つようなものは何もない。空虚な自分から目を逸らす現実逃避なのである。
売れないこと、手に取ってすらもらえないこと こんなことは私の趣味書き人生においてザラだし、私の周りにいる人、いた人、おそらくこれから親しくなる人だって、ほぼほぼ同じだろう。だがこの焦れるような時間を経験することで、私たちはますます強くなり、なおかつそのような時間の連続にも卑屈にならずに文芸を続けることができたなら、いつか海路に日和がくる と信じたい。これは切なる願いである。
けれども、現実に卑屈にならずに生きることの難しさといったら。私がしばしば耳にする「分かる人だけ分かればいい」という言葉は、誠実さのほとばしるような感じがして聞こえは好いが、現実には虚しさが漂う。「分かる人だけ分かればいい」ものは、はじめから分かる人にだけ渡せばいいのである。リリース後に言っても、ねえ。気持ちは分かるけど。
閉塞感なんてお構いなしに、頑固に己を貫き通し、周囲の調子に決して揺るがず、求める道を邁進する そんな生き方ができればそれにこしたことはない。でも人はなかなかそう強くあれるものでもない。そのことを考える時、私がいつも思い出すのは八代目林家正蔵である。
八代目林家正蔵を私はリアルタイムで観たことはない。けれど、たくさんの口演がCD等で残っているので、比較的良い音質で往時を聴くことができる。独特のぶるぶる声、いかめしい佇まいは、いかにも頑固な伝統芸の求道者である。
この師匠、没後どのくらい経てか知らないが、他の噺家たち(むろん正蔵師匠より若い)からしばしばネタにされる。現在ベテランクラスの師匠連が、本や落語のマクラでこんなことを言っている。
正蔵師匠が受けたこと? ないよないよ。トリでさらったなんて、一度たりとも見たことない。
その日、いつも受けない正蔵師匠がいつも以上に受けなかった。
「戸田の渡しは雪でござい」って、なんなんだろ?
ヒドイ言われ方だ。
「ホントにそうかな?」
そう思って改めて聴いてみると、確かにあんまり笑うところが無い。録音の場合、客席も同録されるが、そこにも笑い声が無いので、寒々しいことこの上ない。
けれども正蔵師匠の噺は他の噺家のそれとは一線を画している部分がある。正蔵師匠の噺は「笑う」ものというより、「聞く」ためのものではなかろうか。客席が静かなのも、みんな聞きいっているからなのだ。もっとも、声がぶるぶるしているので聞き入らないと何を言っているのか分からないという点は否めない。
当の正蔵師匠はどう思っておられたのだろう。他の演者の時と比して、客席の温度差は明らかだったと思う。正直私も長いこと「正蔵さんはつまんない」と思っていた。だが、いくつか噺を聴くうちに「これは」という発見をしたことがあった。
それは「ちきり伊勢屋」の聞き比べをした時だった。
ピックアップした演者は圓生・志ん朝・正蔵の三者。圓生は最初に聴いたので評価基準に落ち着いた。志ん朝は彼らしくなく問題外だった。最後に期待せずに聴いた正蔵師匠の口演 ラストシーンの鮮やかさといったら! 情景が目に映るようだった。圓生も志ん朝も一気に色褪せた。朴訥とした語りの中に、登場人物の熱っぽさが生々しく描かれていた。
だが、正蔵師匠の「ちきり伊勢屋」はプロットをかなりアレンジした内容だったので、最初に聴いていたら噺の意味すら分からなかったかもしれない(その点圓生師匠は丁寧でどんな噺でも最初から聴ける)。再度聞くと、ちょっと無理があると思うくらいの長口上や、無理なカットワークも無くは無い。
しかし、確かに私は初聴きで正蔵師匠の口演にビリリと来たのである。
正蔵師匠の落語は、ある程度聴きこんでいる人の耳にしか伝わらない部分があるように思われる。それはおそらく現代に絶滅しかけている落語耳、視覚メディアがほぼ皆無の時代、想像力逞しい明治大正昭和初期のオーディエンスだけが持ち合わせていた耳の良さである。正蔵師匠の口演は、通耳ありきの芸なのかもしれない。だとすると、私が「つまらない」と流し聴きしていたネタにも、実は正蔵師匠の果てしない芸が詰まっているのではないか そう思うと、はて奥の深いものである。
圓朝最後の直弟子・三遊一朝を頂き、廃れなんとする道具立て芝居噺を続け、最後まで圓朝噺に取り組むなど、正蔵師匠の落語の求道者としての横顔はどこまでも真摯である。とりわけ一朝に落語を学ぶことは、近代落語の祖・圓朝と合一たらんとすることで、そのことが師匠の頑ななまでの精神性を形づくったのではないだろうか。くわえて「トンガリ」と呼ばれた馬楽時代や、彦六に名前を変えた経緯などを考えると、筋を通そうとする真っ直ぐな性格が正蔵師匠自身をますますストイックにしていったのではなかろうか。だから周りがどれだけ揶揄しようと、客席が水を打ったように静かだろうと、「おォれェは、おれェの落語をャあルぅぞゥお~」と、頑固一徹に己の落語を貫き通すことができたのだろうと思う。
でも、そんな師匠が「ステテコ誕生」という鼻の円遊の珍芸出世譚を演るってのは どこかああいう芸にも憧れがあったのかもしれない。
正蔵師匠は持ちネタは多からず少なからず。以前何かの本で、立川談志がある師匠を評して「持ちネタが多い? 売れなかったってことだろ」と喝破し胸のすく思いがしたが、晩年ぶるぶる声の正蔵師匠も若いうちは声にみずみずしさがあり、噺も丁寧で、そこそこ人気があったと思われる。「中村仲蔵」「死ぬなら今」「お血脈」「戸田の渡し」……地語りの多いネタが多い気がする。あと廓噺。大のお勧めは「五人廻し」である。国立劇場の録音は客席もノッていて師匠もノリノリの感がある。
*
とまあ、八代目林家正蔵の一途な落語求道を通して、芸道に励む者の在り方を模索してみたわけだが、結局のところ分からんね。芸人は売れなきゃダメだ これは志ん朝師匠が言っていた言葉だが、まこと真理であると思う。売れることで欲が出る、良い意味でプレッシャーにもなる。結果、芸が向上する。売れなければ卑屈になり、ダメになっていく一方だ かの志ん朝ですら、閉塞感の及ぼす精神の矮小化を怖れていたのかもしれない。
誰もが正蔵師匠のようにストイックにはなれない。漠と立ち込める不安の中で己を保ち努力を重ねている時だけが、安心感を覚えられる。倦まず厭わず、飽きずにやってくしかない。
ただし、努力は自分を裏切らないが、成功を約束するものではないことを、忘れてはならない。
おしまい。